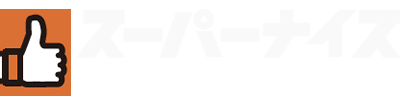Marshallがこじ開けたハイゲインアンプの扉。その扉をくぐって広まったのが80年代以降に登場したハードロック、ヘヴィメタルと呼ばれる音楽でした。このジャンルは商業的成功を収めた80年代以降も常に一定の支持を集め続け、現在も根強くロック音楽の一角を占めるに至っています。
2000年代以降はジャンルのバリエーションも多岐に渡り、
など、様々なジャンルが棲み分けをしながら存在しています。今回はそんな音楽に最適なアンプの特集です。
メタルにもっとも必要とされる条件は、言うまでもなくハイゲインであることでしょう。シャリシャリにならず、ある程度芯を残した状態でのハイゲインが求められますが、アンプメーカーはそのような音像を得るために努力しながら製品開発をしています。最近ではダウンチューニングや7弦、8弦ギターの使用に伴い、低音弦側の周波数も延長される傾向にあり、低域がぼやけずタイトに再生されるという条件を入れてもいいかもしれません。ドラムの音量が大きいため、大出力であることも求められます。ジャズ用のアンプのような出力では演奏しきれないのは言うまでもありません。
メタル系は美しいクリーントーンを軸としたセクションと、凶悪なセクションが対比されてドラマティックに楽曲が作られているものも多く、濁りのない澄んだクリーントーンが必要になってくることは少なくありません。90年代によく見られたモダン・ハードロックにおいても、Bメロだけはクリーンのアルペジオ、バラードだけはクリーントーンなど、明確な使い分けがなされていました。
また、中域を削った、いわゆるドンシャリといわれるサウンドでバッキングのリフを刻み、ソロではミッドブーストさせて音像をせり出させるという使い方は今も昔もよく見られます。そのためEQが独立したハイゲインのチャンネルが二つ以上あると非常に心強く感じます。これはエフェクターでも代用できるため、絶対的なものではありませんが、このような運用ができるアンプは使い勝手の面では一歩先を行くと考えて良いでしょう。
上に記した二つの条件に当てはまるアンプの中でも、特に定番として使われているものをまずはピックアップします。伝統的にヘヴィメタルが盛んなヨーロッパのメーカーはハイゲインモデルに強く、特にドイツはメタル系アンプの宝庫と呼んでいいほど、優れたブランドが数多く存在します。
 Dual Rectifier
Dual Rectifier
90年代初頭にDual Rectifierとして登場以降、ハイゲインアンプの定番中の定番となったMESA/Boogieの看板商品。整流管に真空管を搭載したことからその名が付いたこのモデルは、スラッシュメタル勢を始め、シュレッド系プレイヤーの人気をかっさらい、以後20年もこのジャンルのアンプの頂点に立ち続けています。2000年以降は独立3チャンネル仕様となり、現在出回っているモデルはこれ以降のものがほとんど。Tripleは150W、Dualは100Wの出力を持ち、2019年現在では出力調整できるマルチワットスイッチや、クリーンチャンネルを2モード、歪みチャンネル3モードから切り替えられるスイッチを搭載、多様化するジャンルに対応出来るようになっています。スチール製のパネルに銀色の丸いノブなど、ルックス面にもメタリックな存在感を示し、ザクザクとした切り裂くようなサウンドは、まさにメタルの申し子といって過言ではないでしょう。
Mesa Boogie Dual Rectifier
Mesa Boogie Triple Rectifier

ドイツが生んだアンプブランドであるDiezelから、1994年に登場した記念すべき第一号。メタリカの使用により一役世界中に広まったアンプで、EQなど全て独立の4チャンネル仕様。サウンドは4チャンネルの利点を活かし、切り刻むのようなドンシャリのリフ用サウンドから、中域にややピークを持ってきたソロ用トーン、美しいクリスタルクリーンまで思いのまま。DEEPという特殊なコントロールでは、低域のタイトさをかなり広く制御できるため、多弦ギターにおける極低域の再生にも強い力を発揮します。各チャンネルに取り付けられたエフェクトループ端子を含めて全てMIDIでコントロールできるなど、操作性は完璧。100Wのパワーを持ち、サウンドの幅広さが故に、凶悪なメタルから、ライトなハードロックまで幅広く使えるアンプです。
Diezel VH-4

Herbertも「VH-4」と同じくDiezelを代表する看板製品。180Wの大出力を持ち、独立3チャンネルの仕様。VH-4との違いは出力、チャンネル数のほか、独自のMid Cutセクションであり、こちらは各チャンネルとは独立した部分として存在しています。これをオンにすることで得られる中域を削ったサウンドは、ザクザクとリフを刻むのにまさに最適なもの。カットする周波数は非常にうまく調整されている印象で、メタル系サウンドを知り尽くしたDiezelならではのコントロールと言うことができます。レベルも別途に調整できるので、中域カットを使わずレベルだけを上げたブーストなどとしても使用可能。DEEPコントロールの存在を含めサウンドの傾向はVH-4と非常に似ており、主に使い勝手の面で自分のスタイルに合わせた導入を考えることになるでしょう。
Diezel HERBERT Mk2

ドイツのEnglは80年代よりハイゲインアンプの開発に着手する老舗のブランド。96年にはRitchie Blackmoreとエンドースし、いち早く幅広いハードロック系ギタリストからの評価を受けるのに成功しました。現在、ラインナップは非常に多数にのぼりますが、中でもエントリーモデルである「Fireball」とこちらの「Powerball」は広く愛されているアンプです。2チャンネルのFireballに比べてこちらは独立4チャンネル仕様であり、細やかな運用に向いています。Englのアンプ全体の傾向ともいえますが、歪みの質が細かく、ザクザクとした印象があり、メタル系のお手本とも言えるサウンドです。EQはクリーンチャンネルとクランチチャンネルで、ベース、ミドルが共用。二種類あるリードチャンネルでは3バンドともが共用と、全てが独立というわけではありませんが、クリーン、クランチはトレブルの調整が重要であり、ハイゲインのサウンドにはミッドブーストが別途装備され、十分なサウンドの調整幅が確保されています。
Engl Powerball II

ヴァン・ヘイレン・サウンドの要として知られる「5150II」アンプの正統な後継品。クリーン、リードの2チャンネル仕様ながら、フットスイッチによるクランチのオンオフができ、実質的な3チャンネルのアンプとして利用できます。5150の元々のルーツは「改造されたMarshallアンプ」であり、歪みの質はそのサウンドを軸としたもの。クリーンサウンドについてはやや細く感じるものの、やや粗めなゴリゴリとした歪みのサウンドは図太く、特別な魅力を持っています。120W出力でエフェクトループ搭載。昔ながらのシンプルな作りですが、非常に手に入れやすい価格でもあり、手軽にハイゲインアンプを調達するにはうってつけの存在です。
Peavey 6505+

ドイツのHughes & Kettner、フラッグシップモデルの「TriAmp」は1995年に登場しました。2度のバージョンアップを経てこの「Mark 3」を冠した本機は、現代のメタルに十分対応できるスーパーハイゲインを搭載。3チャンネル仕様ながら、各チャンネルごとにA/Bの2種類の音を切り替えることができ、実質6チャンネルとして使えるサウンドの幅広さを実現しています。使う真空管を任意に選べるという特殊な機能を持ち、それをプログラムして付属のフットスイッチで自在に切り替えることもできるので、あらゆるシチュエーションで様々な使い方に合わせていくことができます。パワー管6本を使って150Wと余裕の出力を持ち、ノイズゲートやブーストも別途装備。単一のアンプとは思えない使い心地はこの上ない魅力でしょう。
Hughes&Kettner TRIAMP MARK3

ハイゲインアンプのパイオニアでもある、Marshallの最新機種。「JCM800」から始まるハードロックアンプの正統な進化形であり、クリーン、クランチ、ドライブx2の4チャンネル仕様。各チャンネルごとに3つの違うモードを持ち、サウンドの幅広さは歴代のMarshallでもトップクラス。往年のJCM800に見られるブリティッシュ系クランチサウンドから、強烈なハイゲインまでを作り出すことができ、特にハイゲインは前モデルの「JCM2000」からもさらなるゲインアップが図られています。ゲインを上げて強烈な音色を得ても中域は一定以上の存在感を保ち、シャリシャリにならないように絶妙なチューニングが施され、それでいてMarshall特有のジャキジャキ感を失っていないのはさすがの一言。必要十分な100W出力にして、Marshallの正統モデルが比較的低価格で手に入るのも嬉しいところです。
Marshall JVM410H

メタル系アンプが得意なドイツ製アンプの中でも、超音速という意味を持つBognerのUbershallは、2001年に「改造Marshall」の音を蘇らせるべく登場。その強烈な名前の通り、非常に過激なサウンドが得られるモデルです。強力なハイゲインを得るモードと、透き通ったクリーントーンの2チャンネル仕様で、コントロールはいずれも4バンドのEQとボリューム、ゲインのみ。昨今複雑なコントロールや4チャンネル以上を持つアンプが多い中、意外なほどにシンプルなコントロールは、どこにセッティングしても使える音が得られるというメーカーの自信の表れとも考えられます。強烈なハイゲインは低域の再生を視野に入れた設計がなされており、多弦ギター、バリトンギターなどでも無理のない再生能力を発揮。目一杯歪ませても芯をしっかり残したサウンドはまさにBognerの真骨頂です。出力はパワー管の種類に従い、100Wと150Wと選ぶことができます。
Bogner Uberschall

小型の練習用アンプから破壊的なハイゲインを出す大出力のヘッドまで、多彩なラインナップを誇るイギリスのBlackstar。こちらは4本のパワー管による100W仕様の、同社のフラッグシップとも言えるモデルです。3チャンネル仕様で、うちドライブチャンネルの二つはEQを共用。艶のあるクリーンから轟音のハイゲインまでをカバーします。Blackstarのいまや代表的コントロールでもあるISFは、ブリティッシュ系とアメリカン系のサウンドを調整できるツマミで、これによってサウンドキャラクターを自在に変更可能。ブライトとダークの二種を切り替えられるデジタルリバーブを搭載し、ラインレコーディング用のスピーカーエミュレート出力も備えており、手に入れやすい価格帯にあって、様々な用途に使える汎用性の高い一品です。
BlackStar HT Metal 100

Kochは1988年に創業したオランダのアンプメーカー。フルチューブアンプのみならず、フロア型プリアンプやエフェクターなど、クオリティの高い様々な製品で世界中のギタリストから信頼を得ています。この「Supernova」はそんなKochのフラッグシップモデルに当たり、120Wの出力、独立5チャンネル仕様にして計28個という大量のコントロールで、ずば抜けて幅広い音作りができるのが魅力です。EQが独立した各チャンネルでは、美しいクリーントーンから破壊的なハイゲインサウンドまでをカバー。0.5Wの専用真空管を利用したOTS(Output Tube Saturation)コントロールを使い、出力時のサチュレーションを調整することで、歪みの倍音構成や太さをもコントロールできます。エフェクトループもシリアル、パラレル共に2系統ずつ装備し、拡張性もトップクラス。作れる音の幅広さでは右に出るものはいないでしょう。
Koch Supernova
実際のアンプヘッドはフルチューブアンプが多く、サウンド面での優位では揺るぎないものの、運搬の問題やメンテナンスの問題、また一般家庭で音を出しにくいという環境的な側面から、導入に踏み切れない人は多いでしょう。そんなギタリストにおすすめなのが、小型のアンプヘッドです。昨今、片手で持てるほどの大きさ、重量でありながら100Wを越えるほどの大出力を持つものが増えてきており、家での練習からスタジオリハーサル、さらにはライブ本番までを一台でこなすことも可能です。その中でも、メタル系音楽に十分使えるほどの強力なハイゲインを得られるものを、数種類紹介します。

DV Markは、Mark Bassというイタリアのベースアンプメーカーのギター用ブランド。昨今、小型ながら大出力をもつアンプを多数リリースしていますが、こちらのLITTLE 250Mもまた幅22.5cm、2.6kgの極小アンプヘッドです。このサイズで250Wの大出力を実現、ハイゲインディストーションとクリーンの2チャンネル仕様で、この大きさから想像付かないほどの迫力あるサウンドをたたき出します。DV Markはもとよりベースで培った濁りの無いクリーントーンに定評があり、そこから受け継がれた非常に艶やかなクリーンサウンドは健在ながら、ハイゲインは裏腹に過激に歪み、ザクザクとリフを刻むのにも、伸びやかなリードギターにも十分対応できるでしょう。ラインアウト、エフェクトループも搭載しており、拡張性も必要十分に配慮されています。
DV LITTLE 250M

ナノチューブという独自の技術を使った極小真空管をパワーアンプに利用したフロア型のアンプヘッド。Bluguitarというブランド自体が、ドイツのスタジオミュージシャンThomas Blugの全面監修に基づくもので、実際の経験に裏打ちされた使い勝手の良さが魅力です。クリーン、クランチ、リードの3チャンネルを本体のスイッチで切り替えることができ、リードチャンネルのゲイン幅はかなり広く、滑らかなリードサウンドからメタル系のリフをザクザク刻めるまでをカバーします。Thomas Blugは一時期Hughes & Kettnerのサウンド顧問を務めており、歪んだ音色の傾向はそれに近いものを持っています。リバーブとブーストを内蔵し、エフェクトループ、ラインアウトも完備、さらにハイゲイン派にはノイズゲートの標準装備が嬉しいポイントです。A5の書類並のサイズに1.2kgという軽量で、可搬性は最高。100Wの大出力を実現しています。
BluGuitar AMP1

小型のアンプばかりを多数リリースするクィルターの、最もハイゲインが得られるモデルが「Overdrive 200」です。横幅22cm、1.8kgの軽量ボディからは信じられない200Wの大出力を持ち、3チャンネル仕様のうちのドライブチャンネル、あるいはドライブ+クランチチャンネルではかなりのハイゲインを得ることができます。良い意味でトランジスタらしくない、艶のあるクリーントーンもかなり使い勝手の良い音色です。サウンドの傾向として若干明るめであり、ザクザクといった類の印象は薄いため、メタル系の中でも合うものと合わないものがありますが、自分のスタイルに合いそうであれば、低めの価格設定もあって、比較的導入しやすいでしょう。クセのあるEQは慣れるまで少し使いにくいですが、このサイズでありながらエフェクトループも備え、実戦でも十二分に活躍します。
Quilter Overdrive 200を…
Sサウンドハウスで探す

「IRT-STUDIO」というラック型のアンプヘッドに端を発し、一回り小型ながらサウンドはそのままに大出力に対応したのが「IRT-SLS」です。ハイパワーモードに切り替えることで300Wもの大出力を得ることができます。クリーン、クランチ、リードという3チャンネル仕様で、いずれも付属のフットスイッチでの切替ができます。このサイズでありながらクリーンとリードとのEQが分かれているところも使い勝手がよく、エフェクトループ、ラインアウトなど多数の入出力端子を備え、自宅練習からライブまでをフルにカバーできる汎用性の高さも魅力です。リードチャンネルには最前段にPre-Gainというコントロールがあり、これを上げていくことでジャキジャキとした飽和したサウンドへと変化します。音色の傾向はMarshall JCM900~2000に近く、Marshall系が好きなギタリストであれば特におすすめですが、ザクザクとしたリフの刻みなどにはやや歪み足りない印象を受けるかもしれません。
IRT-STUDIOを…
Sサウンドハウスで探す
 プロファイリングアンプ「KEMPER」
プロファイリングアンプ「KEMPER」
従来からマルチエフェクターなどに搭載されていたアンプシミュレーター。2010年代以降は技術のすさまじい進化により、高価な機器であれば本物と遜色ないほどの音が出せるようになってきました。先鞭を付けたのはFractal Audio System社のAxe-Fxでしたが、「Kemper」と「BIAS」という二つの製品については、大出力パワーアンプを内蔵したモデルをラインナップし、いずれも通常のアンプとほぼ同じ使用感をもって使えるようになっている点で、明らかにギタリストによる生の演奏を意識した機器となっています。チャンネル切り替えに近い感覚で、複数のアンプモデルを使うことができ、ギタリストにとっては通常のアンプとは全く違う、新たな選択肢の登場となりました。
未来のギターアンプを手に入れよう!プロファイリングアンプKEMPERについて
Positive Grid BIAS Head
BIAS Mini Guitar
音を作る上での要となるプリアンプと、パワーアンプを別で用意して使う方法もあります。利点はプリアンプ側の選択肢の幅が非常に広くなることと、機材を軽量に抑えられることです。デメリットはその逆にパワーアンプの選択肢がかなり少ないことや、プリとパワーとの相性の問題が考えられます。スタジオやライブハウスに常備されているアンプのエフェクトリターンから接続することで、アンプのパワーアンプだけを利用できるので、JC-120などを再生用に使い、プリアンプだけを携帯して演奏に臨むギタリストもいます。
上記紹介したDiezelのハイゲインアンプ「VH4」「Herbert」のフロアタイプ・プリアンプ
多彩な選択肢が得られるプリアンプについては、まずフロア型のプリアンプ機能を搭載したエフェクターが考えられます。アンプのオススメモデルで触れたDiezel VH4、Herbertなどはアンプサウンド直系にして同じ名前のプリアンプがリリースされていますし、Hughes & Kettnerの銘機「Tubeman」はアンプに劣らないほど有名です。なかでもKochはアンプメーカーでありながら「Pedaltone」「Superlead」など、フロアタイプのプリアンプペダルに力を入れています。ほかにも、切れ味の鋭い歪みを持つOrangeの「Bax Bangeetar」はハードロック系などに、強烈な歪みが得られるAmptweakerの「Tightmetal」やiSP Technologiesの「THETA」などは、モダンなメタル系にも対応でき、選択肢の幅は他にもかなり幅広く存在します。いずれもエフェクターボード内で音色作りがほとんど完結できるという点において、大いに魅力のある選択でしょう。
フロアタイプ・プリアンプ特集 – Supernice!エフェクター

アンプシミュレーター系の製品でプリアンプを代用することも可能で、アンプシミュレーターを内蔵した通常のマルチエフェクターの他、「Fractal Axe-Fx」や「Line6 Helix」、「BOSS GT-1000」などの高品質なギタープロセッサー系の製品を使うことで、実際のアンプサウンドと遜色ないクオリティのサウンドが得られます。上で紹介したKemperやBIASも同じような発想であり、昨今は技術の発展のため、ハイゲインサウンドでもこのような選択を行うギタリストが増えてきています。
このケースであれば、エフェクターを兼ねられるという、とてつもない利点が存在します。サウンドを全てそれで完結できるため、最終的には非常に軽量に収まることが多く、メモリーや足下周りを含めて自由自在の操作性をも手に入れられますが、一度作ってしまった音を変えるのが面倒というマルチエフェクター特有の欠点も同時に抱えることになります。
最高峰のサウンドを手に入れよう!ギタープロセッサー特集 – Supernice!エフェクター
《一台で複数のアンプ&エフェクト・サウンドを》モデリング・アンプの魅力 – エレキギター博士
プリアンプと合わせるためのパワーアンプです。オーディオ、PA用だと無数に存在しますが、今回はギター用として作られているものを選びました。
メタル系のアンプはハイゲインで大出力であることが大前提ですが、チューブアンプでは真空管の本数も増えていくため、製作が難しく値段も上がりがちです。そんな中でも現在では随分と選択肢の幅は増えており、接続端子の種類や操作性の面でも、各社様々な部分を改善しながら開発を行っています。
巨大なヘッドとキャビネットは必ずしも必要ではなくなってきていますが、その組み合わせで出す轟音には他にはない魅力があるのも事実。また、足下のプリアンプに小さなパワーアンプだけの小型システムは、実用面においてはおおいに助けとなります。自分のスタイルに合わせて納得のいく機材選びを進めてみましょう。
ドンシャリを愛する全てのギタリストへ!「1万円以下」のメタル系ディストーション11選! – ギターニュース.com
ハイエンド・メタルディストーション・ペダル特集 – Supernice!エフェクター
メタル・ミュージック志向のギター特集 – エレキギター博士
未来のギターアンプを手に入れよう!プロファイリングアンプKEMPERについて
Bluetooth機能を搭載したギターアンプ/スピーカー8選




 (評価686人, 平均値:3.61)
(評価686人, 平均値:3.61)



 (評価648人, 平均値:3.49)
(評価648人, 平均値:3.49)



 (評価515人, 平均値:3.56)
(評価515人, 平均値:3.56)



 (評価494人, 平均値:3.53)
(評価494人, 平均値:3.53)



 (評価418人, 平均値:3.51)
(評価418人, 平均値:3.51)



 (評価390人, 平均値:3.71)
(評価390人, 平均値:3.71)



 (評価363人, 平均値:3.59)
(評価363人, 平均値:3.59)



 (評価317人, 平均値:3.50)
(評価317人, 平均値:3.50)



 (評価310人, 平均値:3.49)
(評価310人, 平均値:3.49)



 (評価304人, 平均値:3.62)
(評価304人, 平均値:3.62)